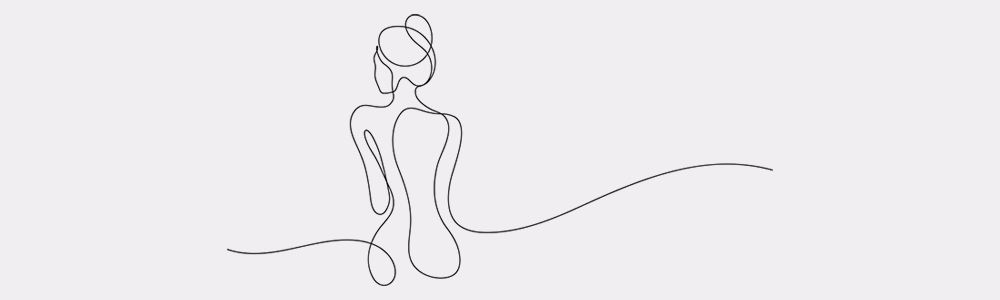
セルフダーマペンは実際どう?セルフで行う危険性やダーマペンで効果を得る方法をご紹介します!
2025.08.07美容皮膚
- 専門医が届ける最新トレンドと知識 -
自分のニオイが気になっているという方は意外と多いものです。
「人よりもワキのニオイが強い気がする」
「脱いだ後の服が臭う…」
などと相談に来られる方が後を絶ちません。
今回はワキガに悩む日本人の人口やワキガの特徴をご紹介します。
「自分ってワキガかも?」「周りに不快な思いをさせていないか心配…」
そんな不安を抱えている方は少なくありません。この記事では、ワキガに悩む日本人の割合や世界的なワキガ人口の違い、ワキガが引き起こす心理的ストレス、そして日本で主流の治療方法について、美容外科医の視点から詳しく解説します。
症状が軽度の場合はセルフケアで改善できることも。まずは「気にしすぎていないか」「治療が必要なレベルか」を一緒に整理していきましょう。
.png)
毎日入浴するという習慣を持つ日本人。
世界基準で見ても日本人はきれい好きで、やや潔癖さを感じる民族として有名です。
そんなきれい好きな日本人は、ニオイにも敏感になる傾向があります。
身体のニオイのうち、汗や加齢臭など気になるニオイは多数存在します。
その中でも、ワキガに悩む方は意外に多いです。
特に、最近はワキガ対策をうたう商品が多数販売されていることから、ワキガが気になる方が多いことは明白ですね。
日本人は、他人のニオイに敏感な方が多いため、自分のニオイに対しても必要以上に気にします。
「ニオイが気になって緊張する」「市販グッズが手放せない」
このようにワキガや体臭に悩む方はとても多く、中には日常生活に支障をきたすケースも。
.png)
しかし、日本は他国と比較するとワキガに悩む人が少ない傾向があります。
割合としては10人に1人くらいでしょうか。
中には、自分がワキガであることに気づいていない方も。
ワキガは優性遺伝すると言われています。
周囲の人、特に家族がワキガに悩む人でなければ自分では気づかないかもしれませんね。
ワキガに悩むのは日本人だけではありません。
むしろ、日本や韓国など東アジアはアメリカやヨーロッパに比べるとはるかにワキガ人口が少ないです。
アポクリン腺が発達しているとワキガになりやすいですが、その割合は国や地域、人種や生活習慣によってばらつきがあります。
人口の70~80%以上がワキガの国、10%以下の国などさまざまです。
この数字からわかるように、世界基準で見ればワキガはとても身近なものです。
ですからそこまで気にする必要はないのかもしれません。
とはいえ、ワキガ人口が70%の国で自分がワキガの場合、ワキガ人口が10%以下の日本でワキガの場合では、心理的な意味で感じ方は異なります。
特に、日本人は周りと違うことに敏感ですから、自分が少数派であること、さらにそれが他人に不快感を与えるともなれば、深刻なコンプレックスになってしまいます。
さらに、日本と海外では、ワキガに対する治療方法においても異なります。
日本と海外では、ワキガに対する治療方法が異なります。
海外ではニオイを軽減する治療が多いのに対し、日本ではニオイの原因となる汗腺の摘出が人気です。
日本は「原因を元から絶つ」傾向にあるのかもしれません。
単に汗が多い場合は「腋窩多汗症」、強いニオイを放つものを「腋臭症」と分けて考えています。
つまり、ニオイがあるかどうか、ニオイが強いかどうか、といった基準があることになります。
こうしたことから、日本人にとってワキガの症状は、非常にデリケートで深刻な問題であることが分かります。
.png)
ワキガを過剰に気にすることはストレスにつながるため、決して良い状態とは言えません。
まずは、本当に気になるほどの症状なのかチェックしてみましょう。
自分で確かめるのは難しいので、親しい人に確認してもらいましょう。
正直に答えてもらったうえで「気にならない」と言われたならば、自分が気にするほど強いニオイではないということが分かります。
それでも不安であれば、ワキガ治療を実施しているクリニックに相談しましょう。
ワキガに対する治療方法には「ボトックス注射」や「完全摘出」があります。
そのほか、塗り薬で緩和する方法もあるので、まずは専門医に相談しましょう。
具体的な治療方法や効果が出る仕組みについてはこちらのコラムをご覧ください。
今回はワキガに悩む日本人の割合、ワキガの特徴をご紹介しました。
自分が感じるニオイを他の人も不快に思うかどうかは分かりません。
ワキガはデリケートな悩みですが、正しい知識と対処法があれば不安を軽減することができます。
GBCでは、無理に治療をすすめることなく、患者様一人ひとりの症状と気持ちに寄り添ったご提案を行っています。
「これは治療が必要?」「ただの思い込みかも?」
そんな不安を抱えている方も、まずはお気軽にご相談ください。
あなたにとって最適な解決法を、専門医と一緒に見つけていきましょう。